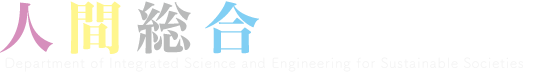ホーテス シュテファン 教授
Stefan Hotes
景観環境科学研究室
<専門分野>
景観生態学、環境科学、持続可能性科学
<研究テーマ>
持続可能性の観点から環境を分析・計画する
Google scholar page※2019年4月に着任
Profile :
湿地や農地、森林などを対象に、生態系と人間社会の相互作用を研究。ドイツ・レーゲンスブルグ大学にて博士号(理学)取得。イギリス・東 ロンドン大学健康及び生命科学研究科講師、東京大学大学院農学生命科学研究科 特任研究員・助教、ドイツ・ギーセン市ユストゥス・リービッヒ大学研究員、マールブルグ市フィリップス大学研究員を経て、2019年より中央大学理工学部教授として着任。ランドスケープ科学・持続可能性科学に関する学術論文に加えて実践者向けの図書も発表。国際連合の生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)のステークホルダーネットワーク構築に積極的に関わっている。学生に期待する
3つの資質
- 資質1自然と人に向けるまなざしの優しさ
- 資質2多様な対象・事象への探求心
- 資質3思いがけない変化に対応できる順応性
生態学から持続可能な社会を考える
持続可能性という観点
 人間と環境の相互作用を持続可能性の観点から捉えています。持続可能性科学という学問は人と自然の関わりを網羅し、異分野を統合する包括的な研究領域です。本研究室ではこの幅の広い分野に理工学の手法を用いて貢献し、人の考え方や行動(社会学、心理学、経済学など)を研究する専門家とも協力します。持続可能性は生態系や社会系などといった複雑な「系」の安定性や動態、特に攪乱後の回復力(Resilience、レジリエンス)と深い関係があります。レジリエンスはどのような条件下で保たれ、どのような時に失われるかを解明することは持続可能性に関する基礎研究の最終目的です。
人間と環境の相互作用を持続可能性の観点から捉えています。持続可能性科学という学問は人と自然の関わりを網羅し、異分野を統合する包括的な研究領域です。本研究室ではこの幅の広い分野に理工学の手法を用いて貢献し、人の考え方や行動(社会学、心理学、経済学など)を研究する専門家とも協力します。持続可能性は生態系や社会系などといった複雑な「系」の安定性や動態、特に攪乱後の回復力(Resilience、レジリエンス)と深い関係があります。レジリエンスはどのような条件下で保たれ、どのような時に失われるかを解明することは持続可能性に関する基礎研究の最終目的です。協同の重要性
 人間社会が気候変動や生物多様性の減少、経済格差など多くの互いに関連を持った課題に直面している中で、学術的な手法によって得られた知見を様々な主体と共有し、持続可能な生活様式を巡る議論に積極的に参加することが期待されています。本研究室ではこの社会の期待に応えられるように、いろいろな場で活躍している実践者と交流し、協力体制を作っています。例えば、野生生物の分布や個体数などといった自然現象を研究する場合に市民科学者と協力し、情報通信技術の進歩によって手に入った新たな可能性を利用し、今まで把握することができなかった社会生態系の動態の仕組みを解明することに挑戦します。
人間社会が気候変動や生物多様性の減少、経済格差など多くの互いに関連を持った課題に直面している中で、学術的な手法によって得られた知見を様々な主体と共有し、持続可能な生活様式を巡る議論に積極的に参加することが期待されています。本研究室ではこの社会の期待に応えられるように、いろいろな場で活躍している実践者と交流し、協力体制を作っています。例えば、野生生物の分布や個体数などといった自然現象を研究する場合に市民科学者と協力し、情報通信技術の進歩によって手に入った新たな可能性を利用し、今まで把握することができなかった社会生態系の動態の仕組みを解明することに挑戦します。SDGsとIPBESの試み
 地球規模の持続可能性を確保するためには土地や自然資源の利用を把握し、これらの人間活動が引き起こす効果を定量化する必要があります。国際連合の「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)がそのための一つの枠組みで、地域計画、都市計画などにおいても取り上げられるようになっています。SDGsと並行して、例えば「政府間生物多様性及び生態系サービスプラットフォーム」(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)を通じて社会生態系評価が実施され、このプラットフォームの活動に関わっています。
地球規模の持続可能性を確保するためには土地や自然資源の利用を把握し、これらの人間活動が引き起こす効果を定量化する必要があります。国際連合の「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)がそのための一つの枠組みで、地域計画、都市計画などにおいても取り上げられるようになっています。SDGsと並行して、例えば「政府間生物多様性及び生態系サービスプラットフォーム」(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)を通じて社会生態系評価が実施され、このプラットフォームの活動に関わっています。持続可能な社会をつくるための幅広い連携
 本研究室では、社会生態系の仕組みを解明し、研究で得られた知見を、地域活動から国際的な政策にまで応用することを目指します。異なる分野の学問との協力を重視し、政策担当者・行政・企業・市民など実践の場で活躍している人と連携し、理論と実践の統合に意欲をもって取り組める学生を歓迎します。
本研究室では、社会生態系の仕組みを解明し、研究で得られた知見を、地域活動から国際的な政策にまで応用することを目指します。異なる分野の学問との協力を重視し、政策担当者・行政・企業・市民など実践の場で活躍している人と連携し、理論と実践の統合に意欲をもって取り組める学生を歓迎します。ホーテス研を理解するためのキーワード4
-
1. 人新世(Anthropocene)
 人間が地球上のあらゆるプロセスに大きな影響を与えるようになった今の時代を記載するために、「人新世」という用語が作られました。人新世の特徴として、世界人口の急激な増加や一人当たりの自然資源の消費の上昇、大量生産・大量消費に伴う廃棄ガス、ゴミの増量などが挙げられます。都市化が急速に進行するのも人新世を象徴する現象です。化石燃料など地下資源の膨大な利用や農業・林業・水産業の集約化によって生物多様性が減少し、物質循環に変化が起き、地球上のエネルギー収支が変わりつつあります。これは、我々人間の営みが地球生態系の生産能力や廃棄物を分解・処理する能力を超えていることを反映しています。人類が長期的に存続できるためには、地球生態系の容量に合わせた生活様式を実現する必要があります。つまり、持続可能性を確保しなければなりません。
人間が地球上のあらゆるプロセスに大きな影響を与えるようになった今の時代を記載するために、「人新世」という用語が作られました。人新世の特徴として、世界人口の急激な増加や一人当たりの自然資源の消費の上昇、大量生産・大量消費に伴う廃棄ガス、ゴミの増量などが挙げられます。都市化が急速に進行するのも人新世を象徴する現象です。化石燃料など地下資源の膨大な利用や農業・林業・水産業の集約化によって生物多様性が減少し、物質循環に変化が起き、地球上のエネルギー収支が変わりつつあります。これは、我々人間の営みが地球生態系の生産能力や廃棄物を分解・処理する能力を超えていることを反映しています。人類が長期的に存続できるためには、地球生態系の容量に合わせた生活様式を実現する必要があります。つまり、持続可能性を確保しなければなりません。 -
2. 持続可能性(Sustainability)
 「持続可能性」には様々な意味が含まれていますが、人類の未来を巡る国際的な議論においては、持続可能性を包括的に捉え、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」(meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)と定義しています。この理想に近づくためには、社会や経済、環境という要素からなる「社会生態系」(socio-ecological system)の仕組みを理解することによって人類の「安全な活動範囲」(safe operating space)を把握し、政策や計画の立案、企業の運営などにおいて考慮する必要があります。具体的には、過去における環境や社会の変動を参考にしながら、予想外の出来事も視野に入れて、将来起こり得ることに関するシナリオを作ります。シナリオをモデルと組み合わせて、可能な限り正確に将来の社会生態系の変動を予測します。予測から得られた知見を共有し、幅広く順応的な管理に活かせば、包括的な意味の持続可能性を探り続けられます。つまり、持続可能性は「状態」ではなく、「プロセス」です。
「持続可能性」には様々な意味が含まれていますが、人類の未来を巡る国際的な議論においては、持続可能性を包括的に捉え、「将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと」(meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)と定義しています。この理想に近づくためには、社会や経済、環境という要素からなる「社会生態系」(socio-ecological system)の仕組みを理解することによって人類の「安全な活動範囲」(safe operating space)を把握し、政策や計画の立案、企業の運営などにおいて考慮する必要があります。具体的には、過去における環境や社会の変動を参考にしながら、予想外の出来事も視野に入れて、将来起こり得ることに関するシナリオを作ります。シナリオをモデルと組み合わせて、可能な限り正確に将来の社会生態系の変動を予測します。予測から得られた知見を共有し、幅広く順応的な管理に活かせば、包括的な意味の持続可能性を探り続けられます。つまり、持続可能性は「状態」ではなく、「プロセス」です。 -
3.レジリエンス(Resilience)
 レジリエンスというのは、簡単に言えば「回復力」を指しています。何等かの攪乱が起きた後で、攪乱によって変わった物事が元の状態に戻ろうとする傾向を指しています。生態系においては、例えば台風や火事、植物を食べる昆虫の大発生などによって植生が大きく変わった後で、元の植生が回復する速さを測り、レジリエンスを定量的に把握できます。回復するのが速いと、レジリエンスが高い、遅いと、レジリエンスが低いことになります。生態系と似たように、社会系・経済系においても、自然災害や人間が起こす急激な変化によって、社会の構造が崩れたり、経済活動が妨げられたりすることがあります。社会や経済の機能性を表す指標を時系列で測ることによって、社会や経済が元の状態に戻る速さやそのメカニズムを明確にし、レジリエンスの評価に使います。レジリエンスについて理解するのは、持続可能性の実現に向けた順応的管理において重要なことです。
レジリエンスというのは、簡単に言えば「回復力」を指しています。何等かの攪乱が起きた後で、攪乱によって変わった物事が元の状態に戻ろうとする傾向を指しています。生態系においては、例えば台風や火事、植物を食べる昆虫の大発生などによって植生が大きく変わった後で、元の植生が回復する速さを測り、レジリエンスを定量的に把握できます。回復するのが速いと、レジリエンスが高い、遅いと、レジリエンスが低いことになります。生態系と似たように、社会系・経済系においても、自然災害や人間が起こす急激な変化によって、社会の構造が崩れたり、経済活動が妨げられたりすることがあります。社会や経済の機能性を表す指標を時系列で測ることによって、社会や経済が元の状態に戻る速さやそのメカニズムを明確にし、レジリエンスの評価に使います。レジリエンスについて理解するのは、持続可能性の実現に向けた順応的管理において重要なことです。 -
4. 生態系サービス(Ecosystem Services)
 生態系サービスとは、生態系のはたらきを介して生み出される、人間社会にとってのあらゆる便益を指します。すなわち、自然の恩恵です。これらの恩恵を定量的に把握するために、生態系サービスの概念が導入されました。この概念においては、人間社会と生態系との相互作用が整理され、三つの基本的なサービスのタイプが区別されます。この三つのタイプは「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」と呼ばれています。供給サービスは農地や森林、湖や海などから得られる食糧や材料、飲料水などを指し、調整サービスは植生による気温や水循環の安定化、水質の浄化、野生生物の個体数の増減の制限など生態系における様々なプロセスの制御効果を表します。文化的サービスには、人の精神の高揚や、やすらぎを与える効果が含まれています。上記の三つの分類単位に加え、生態系の仕組みを支える基礎的な機能、例えば光合成による生産や受粉などを「基盤サービス」として区別することがあります。生態系サービスを正確に把握するのは人新世に適した人間社会の発展において緊急な課題です。
生態系サービスとは、生態系のはたらきを介して生み出される、人間社会にとってのあらゆる便益を指します。すなわち、自然の恩恵です。これらの恩恵を定量的に把握するために、生態系サービスの概念が導入されました。この概念においては、人間社会と生態系との相互作用が整理され、三つの基本的なサービスのタイプが区別されます。この三つのタイプは「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」と呼ばれています。供給サービスは農地や森林、湖や海などから得られる食糧や材料、飲料水などを指し、調整サービスは植生による気温や水循環の安定化、水質の浄化、野生生物の個体数の増減の制限など生態系における様々なプロセスの制御効果を表します。文化的サービスには、人の精神の高揚や、やすらぎを与える効果が含まれています。上記の三つの分類単位に加え、生態系の仕組みを支える基礎的な機能、例えば光合成による生産や受粉などを「基盤サービス」として区別することがあります。生態系サービスを正確に把握するのは人新世に適した人間社会の発展において緊急な課題です。